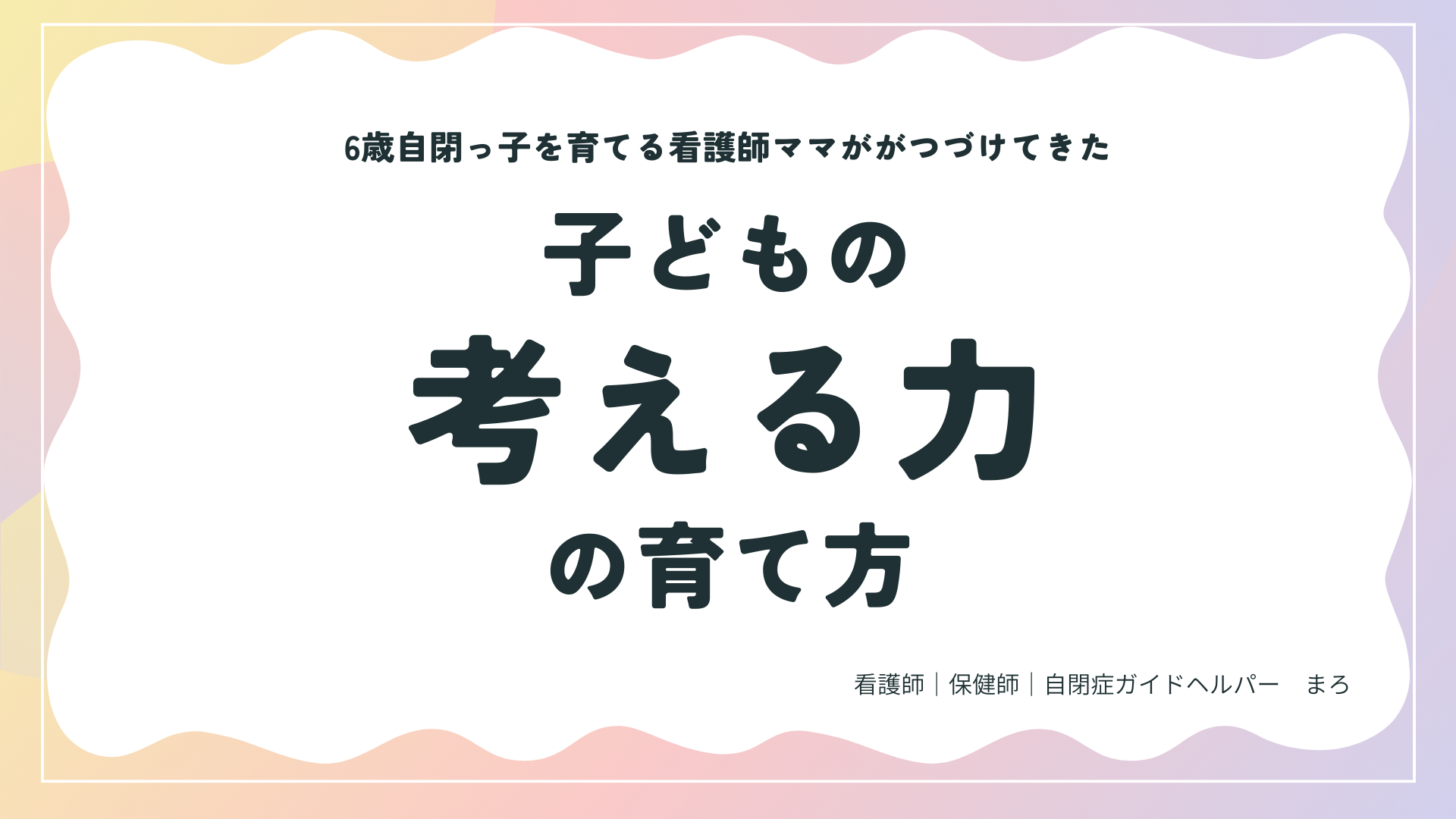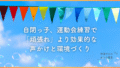『今日も保育園を出るのに30分かかった…』
泣き叫ぶ息子をなだめながら園を出るのに、
毎日ヘトヘト。
先生からは「今日のトラブル報告」を
毎日聞かされて
「早くこの時間、終わってくれ。」
って、毎日思っていました。
おまけに
「あの子いつも騒いでるよね」
っていうママ友同士の
おしゃべりまで聞こえてきて
心が折れそうでした。
当時の私は、

「育て方悪いのかな…」
と自分を責めてばかりでした。
受診の時は決まって
時間いっぱいまで
先生にとにかく聞きたいことを
全部ぶつけていました。
かんしゃくばっかりで、どうしたらいいの!?
となっている私にある日先生から、

「息子君の考える力を伸ばしましょう」
と言われたんですよね。
なぜ考える力?と
よくわからないので
詳しく聞いたところ、
息子に必要なものは
「かんしゃく対応」でもなく、
「薬」でもなく、
「視覚支援」でもなく──
『非認知能力を育てましょう』 だったんです。

全然分からないながらも
とにかく先生に言われたことを
信じてやってみました。
今思えば、この関わりが成長のカギだったんだな
と感じます。
今回はそんな『非認知能力』について
我が家ではどんなふうに
おうち療育に落とし込んでいたのか、
お伝えします!
なぜ非認知能力なのか?
非認知能力って難しく聞こえますが、
要は「テストの点では測れない力」。
感情を整える力とか、
人と関わる力とか。

研究でも、集中力や感情を整える力がある子ほど、
学びに向かう姿勢が育ちやすいと分かっています。
我が家がやった5つのこと
実際にやったことは下の5つ。
これを土台にしました。
- 名前を呼んで挨拶する
- 結果より過程をほめる
- 感情に名前をつける
- 「どうする?」を一緒に考える
- 一日の終わりに「大好き」を伝える
これらは一見簡単そうですが、
全て「非認知能力を伸ばす」ことに
つながっています。
そして、この5つの土台があったからこそ、
息子の「考える力」は
さらに伸びたと感じています。
実際のやり方とエピソード
ここからは、実際に
我が家でどう取り組んだのかをご紹介します。

- 名前を呼んで挨拶する
子どもは名前を呼ばれるだけで「自分が大切にされてる」と感じやすいと心理学でも言われています。まずは名前を呼んで「おはよう」と関わりの入口を作ることから始めました。
「○○君、おはよう」って声をかけると、本当に小さい声で「ママおはよ。」とちょっとだけ笑ってくれる息子がとにかく嬉しかったんです。 - 結果より過程をほめる
「できたね」よりも「頑張ってたね」「工夫してたね」と声をかけると、子どもは挑戦を続けやすいと研究で分かっています。息子も結果だけを気にせず「やってみよう」と思えることが増えました。さらに、「ここを特に工夫してみた」という見てほしいポイントも説明してくれるようになってより息子の考え方に興味が出ました。 - 感情に名前をつける
心理学的にはラベリングと言われています。
「怒ってるんだね」「悲しかったんだね」と代弁してあげると、気持ちが落ち着きやすいことが脳科学でも示されています。実際、癇癪の爆発が少しずつ小さくなっていきました。特に小さい時は泣いていても感情が分からないことが多いです。そのため、「泣いてるね、それっててむかつくー!って気持ちだね」と丸っと受け止めて、感情を教えてあげることで息子の感情のレパートリーが増えて、息子と話すことがすごく楽しい!って感じるようにました。 - 「どうする?」を一緒に考える
困ったときに「どうしたい?」と問いかけることで、子どもは少しずつ解決策を考えられるようになります。最初は答えられなかった息子も、繰り返すうちに「次はこうしてみる」と自分から提案できるようになりました。また、「失敗しそうで怖いから見てて」というお願いも出せるようになってきました。 - 一日の終わりに「大好き」を伝える
安心できる関係は、子どもの自信の土台になるといわれています。寝る前に「今日も大好きだよ」と伝えるだけで、息子は安心して眠れるようになり、翌朝の機嫌まで変わってきました。
これらにと組んだうえで
私は先生方とも相談しながら
「助けて」と周囲に言える相談力や
「考える力」を育てることを意識しました。
具体的にご紹介しますね。
さらに踏み込んで考える力へ
さらにこんな声かけを取り入れました。
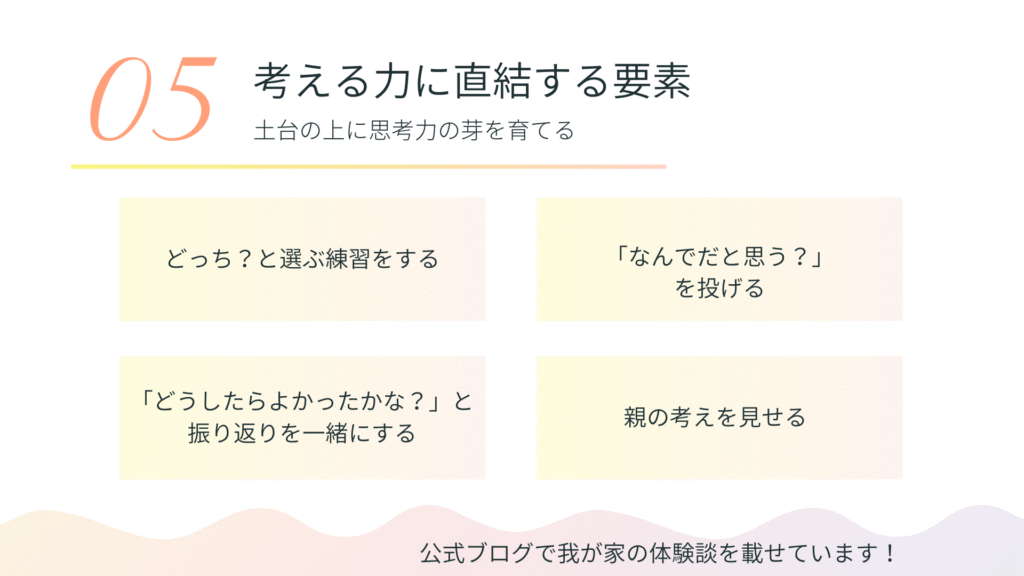
- 選択肢を渡す:「靴下やだ!」→「そっかあ、赤と青、どっちにする?」
→親が枠組みを作りつつ、その中で行う小さな意思決定の積み重ねが「考える力」の出発点。 - なんで?を返す:「なんで雷が落ちるの?」→「どうしてだと思う?」
→ 自分で原因を想像する力が育ちます。 - 振り返りを一緒にする:「どうだった?」「次はどうする?」
→忘れ物をした時に、「次はこうやる。」と自分から改善策を考えるようになりました。 - 親の思考を見せる:「今日は寒いから長袖にするね、もし半そでだったら風邪ひいちゃいそうだしなあ」などと、
→因果関係を含めた親の「考えるプロセス」を言葉にすることで、子どもも「考えるってこういうことか」と学べるんです。
今日からできること
「全部やるのは大変そう…」
と思うかもしれません。

そんな方はまずは 寝る前に
『大好きだよ』と伝えることから
始めてみてください。
安心感はすべての土台。
ここから「考える力」へも
つながっていきます。
2年後の息子の変化
実はこの関わりを意識してから
変わったことが2つあります。
①かんしゃくは半年でほぼ0に落ち着きました。
②「困ってるから助けて」「こう思ってるんだけどやってもいい?」
と相談することができるようになりました。

絶対無理だと思っていた
息子と2人での日帰り旅行や
県外の親戚の家に遊びに行くこと
新しいことに挑戦できるようになって、
お休みの日、何して遊ぶか
ワクワクしながら相談してます。
まとめ
非認知能力は、
ただ「優しい子」
「周りに合わせることができる子」
にするものではありません。
学力や社会性の土台になる、大事な力です。
そしてその一歩はとてもシンプルです。
「名前を呼ぶ」「大好きと伝える」
私も最初はここから始めました。
もし「うちの子にはどう取り入れたらいい?」
と思ったら、
LINEからお気軽に相談してくださいね🌱
今回の関わりをわかりやすくまとめた資料を
公式LINEで配信中です🌸
受け取りはこちらをタップ👇