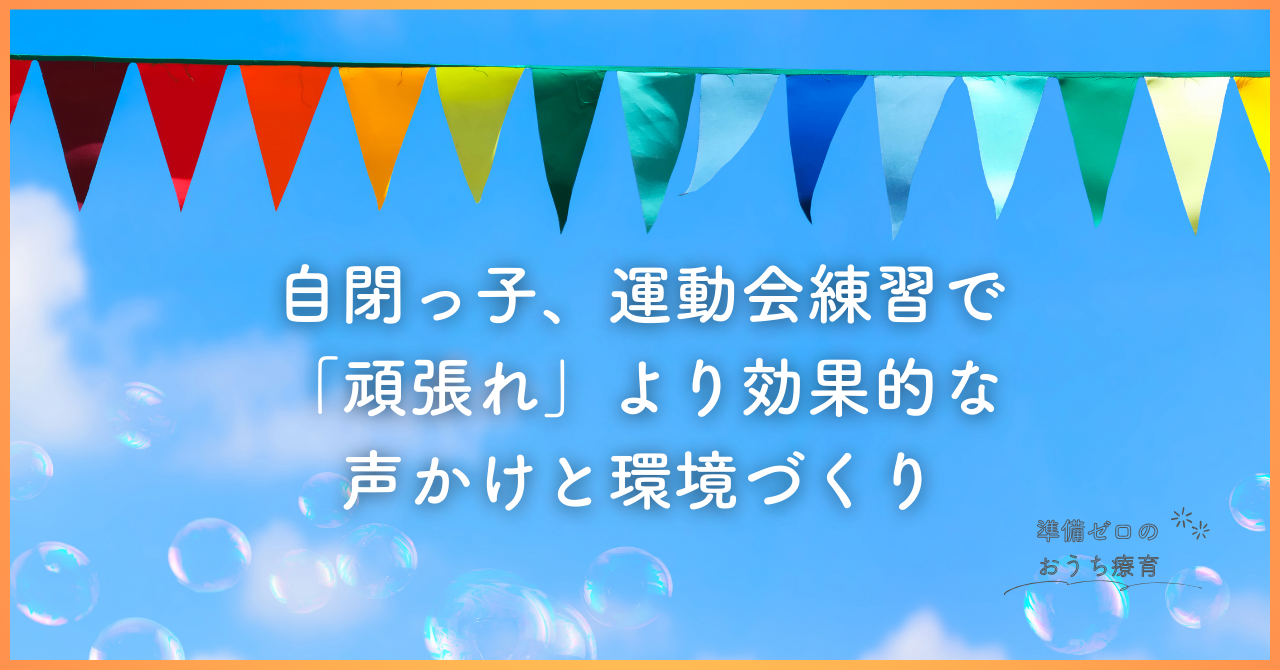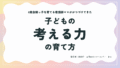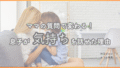運動会といえば、
「秋」というイメージがありますが
最近は5月にやるところもあり
時代の変化を感じる今日この頃です。
皆さん、こんにちは!
まろです。
先日息子の通っていた
保育園の前を通ったところ
運動会のかけっこの練習をしている
子どもたちが見えました。

かわいい~!!!!
と思う反面、
ちょっと苦い思い出と
嬉しい思い出がよみがえりました。
実は息子は、運動会の練習が大嫌い。
毎日泣いて帰ってきていました。
私も最初は
「頑張って!」
「みんなと一緒にできるよ!」
と声をかけていましたが、逆効果。
息子は行き渋りになるように。
結果、運動会の練習に
ほとんど参加できずに
本番を迎えることが
年少、年中とありました。
年長になり、

息子に楽しんでほしい、良い思い出にしてほしい!
という思いから、
おうち以外の力を借りることにしたんです。
その結果、息子は運動会本番で
笑顔を見せることができました。
今日はそんなお話をしますね。
なぜ「頑張れ」が自閉っ子には逆効果なのか?
特に息子は「頑張れ」は
禁句、というレベルで敏感でした。
その理由が3つありました。
1. 感覚過負荷による混乱
息子をはじめ、自閉っ子は
感覚情報の処理が苦手な子が多いです。
運動会の練習では
- 大勢の子どもの声
- 音楽や笛の音
- 体を動かす感覚
- 視覚的な刺激
こんな刺激が一度に押し寄せ、
脳が処理しきれない状態になります。
そこに「頑張れ」という
追加のプレッシャーが加わると、
さらに混乱状態になります。

2. 抽象的な指示の理解困難
「頑張れ」は抽象的な概念です。
自閉っ子にとって
- 何をどう頑張ればいいのか分からない
- 具体的な行動指示がない
- 曖昧さが不安を増大させる
というパニック状態に
なりやすくなるんです。
実際息子も
「○分間、頑張ろう」などの
終わりが見えると
頑張れることがありました。
3. 失敗への恐怖の増幅
「頑張れ」と言われると
「期待に応えなければ」という
プレッシャーが生まれます。
これが失敗への恐怖を増幅し、
挑戦する意欲を削いでしまいます。

息子は特に間違えることが怖くて
逆に練習に参加できない
ということが多くありました。
実際に間違えたとたん床に倒れこんだり
かんしゃくを起こして
練習がたびたび中断していたそうです。

この話を聞いた時は本当に辛いし、園にも申し訳ないし…でした。
効果的だった声かけと環境づくり
そこで私は発達外来と、療育先に
前の年のことも含めて
相談したんです。
すると担当の先生が保育園を視察してくれて
自閉っ子である息子にピッタリのアドバイスを
してくれました。
そこでおうちで取り入れたのが
「具体的で分かりやすい声かけ」と
「環境調整」でした。
- 「右足、左足」などリズムで伝える
- 「手をパーにして振ろう」など動作を具体的に見せる
- 「○分間だけ」「3回だけ」と区切って先を見せる
家庭でも「何回踊るか」を
カウントして伝えるようにしたら、
息子は安心して挑戦できるようになりました。
また、ポケモン完成システムも導入。
カラーイラストを4つに分け、
練習に参加したら1ピースを貼っていく。
全部そろったら「運動会本番!」。
視覚的に進捗が見えることで、
息子のモチベーションにつながりました。

また、間違えたり
繰り返す練習が苦手な息子には
「視覚優位」という特性を生かして
お友達の練習を見学して、
完成形を見てもらってから
練習に参加させてもらいました。
園・療育との連携
息子の変化は、家だけで
何とかしようとせず、
療育の先生に
現場を見てもらったのも大きな転機でした。
- 息子の視覚優位な特性を踏まえて、練習に参加するかどうかは息子自身が決める
- ただし別室にいるのではなく、体育館の隅にいて「完成形を目で覚える」時間を持つ
- 仕上げ段階で合流すると、意外とスムーズに入れる
さらに保育園の先生方は、
息子を「とりあえず端っこ」ではなく、
いなくても形になるけどいたら整うポジション
に配置してくださいました。
これが息子の安心感と役割意識につながり、
張り切って取り組む姿が見られました。

療育・保育園・家庭の3つが
「作戦会議」をして、
同じ方向を向けたことが、
息子にとって大きな支えになったと思います。
こうした積み重ねの結果、
年長最後の運動会では、
息子はすべての競技に参加できました。
そして、園庭の真ん中で
役割を果たしながら、
笑顔を見せてくれたのです。
練習で泣いて帰っていた頃を思うと、
その姿だけで涙が止まりませんでした。

それはそれは泣きました。
「頑張れ」ではなく
「君のペースで、一緒にやろう」。
環境づくりで
息子は大きく変わったのだと思います。
練習に参加できないときは
- 「頑張れ」をやめて「一歩ずつ」「○○のペースで」に変える
- 学校に「家庭で効果的だった工夫」を具体的に伝える
- 視覚的な支援(シール、カレンダー、完成システム)を導入して見通しを作る
「みんなと同じように」
できることがゴールではありません。
「その子らしく参加できる」ことこそ、
最高の成功体験になります。
もし運動会の練習に
困り事があったら、
この視点を取り入れてみても
いいかもしれません。
それではまた次回!
まろでした🌸